ぼくの車は電気自動車。
ガソリンスタンドに行かなくていいって、正直めっちゃ気分がいい。
でも…フル充電しても走れるのはせいぜい100km足らず。県外に出る時はちょっとビビる。

🚀 次に乗りたいのは「水で走る車」!
そんなぼくが、次に乗りたいと本気で思ってるのが「水で走る車」だ!
電気自動車に乗ってる今でも、エコで未来的だな〜って感じるけど、やっぱり充電の手間とか走行距離の不安はつきまとう。そんな中で、水さえあればどこでも走れる車があったらどう?
山奥でも、海辺でも、旅先で水を補給するだけで走り出せるなんて、まさに夢のよう。
しかも、地球にも優しい。そんな車に乗れる未来が来るなら、ぼくは迷わずそのハンドルを握りたい!
🧪 スタンリー・メイヤーって知ってる?
1980年代にアメリカで話題になった発明家、スタンリー・メイヤー。
彼は「水を分解して取り出した水素で車を動かす」という、夢みたいな技術を開発したって言われてるんだ。
普通の水(H2O)に電気を通して水素を取り出し、それをエネルギー源に。しかも、彼の特別な装置なら、すごく少ない電力でそれができるって主張してた。もしそれが本当なら、ガソリンも電気もいらない。水さえあればどこまでも走れるってことになる。
🤔 本当なの?それともウソ?
そんなうまい話、信じられる?
もちろん、科学者たちからは「エネルギー保存の法則に反する」「実験の再現性がない」とバッサリ批判された。
実際、裁判で「詐欺だ」と認定されたこともある。
でも、それでも夢を追い続けたメイヤーの姿勢や、彼の残した技術に今でも魅せられてる人は世界中にいる。
YouTubeで「Stanley Meyer car」と検索すれば、いまでも実験してる人たちの動画がいっぱい出てくるよ。
🚘 すでに存在する水素自動車
そして、現実世界でも水素自動車が走っている。
日本でもトヨタ「ミライ」やホンダ「クラリティ」など、水素を燃料にする車はすでに販売されてる。
でもこれは水を燃料にしているわけではなく、あらかじめ作られた水素をタンクに詰めて走る仕組み。
水から直接エネルギーを取り出すメイヤー方式とはちょっと違う。
それでも、水素技術は着実に進化していて、将来的には「水から直接燃料を生み出す車」も現実になるかもしれない。
🌊 水を入れて走る車の未来
想像してみて!水を入れて走る車の未来。
雨水でも、川の水でも、家の蛇口から出した水でも車が動く世界。
しかも、排出されるのは水蒸気だけ。地球に優しくて、エネルギー問題も解決できる。
さらに、家庭でも電気を作れるようになるかもしれない。
まさに「水が未来のガソリン」になる時代が来る…そんな世界を想像するとワクワクが止まらない!
📌 まとめ
スタンリー・メイヤーの夢は、まだ「幻」と呼ばれているかもしれない。
でも、誰かが無理だって言っても、それを信じて進む人がいるから未来は開けていく。
ぼくは水で走る車に、ほんとうに期待してる。
そんな未来に、ぼくの次の愛車で走り出せたら最高だ。
水で走る車、のりたーい!

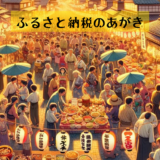

スタンリーメイヤーの水で動く自動車は、本物のフリーエネルギーの可能性があります。
大政氏の研究でブラウンガスとOHMASA-GASの質量分析比較がなされている。
ブラウンガスは水の電気分解装置に正の電圧パルスを加えて、水を電極間に振動させて、その正電極に水素分子を供給して、フェムト水素分子を生成し、電極から降下するフェムト水素分子と、水の流動が電極表面ではフェムト水素分子の降下方向と垂直になり、フェムト水素分子と衝突して核種変換することを用いてブラウンガスを生成させている。ここで留意すべき点は大政氏がブラウンガス生成に用いた装置は水の核種変換装置と結論できる。つまり、水の核種変換機は、パラジウムを電極として用いており、パラジウム金属内ではFCC結晶格子を持つのでフェムト水素分子が生成するからであるが、この点、ブラウンガスは常温核融合の発見以前の発明で、その時代にはSUSを用いていたはずであるが、SUSはFCC結晶格子を持つ種類のものもあるので、その種類のSUSを用いてたまたまブラウンガス(水のフェムト水素分子での核種変換ガス)が生成していたと解釈できる。
そのブラウンガスの質量スペクトルは通常の水の電気分解では生成しない酸素18(質量数18)が明確に検出されており、さらに、クラスターガス質量分析装置ではその原子状酸素18がクラスタ化した質量スペクトルが明確に示されている。H2OのO-16がフェムト水素分子と核融合すると。O-H結合は維持できないので、原子状酸素18となり、それらは水中で接触して酸素18クラスタガスとなる。
大政氏はOHMASA-GASとブラウンガスの区別ができていないので、資料ではOHMASA-GASとの比較になっているが、実際はOHMASA-GASは、は水の低周波撹拌機を水の電気分解装置の両側に設置して、水の電気分解速度を上げただけの、単なる通常の酸素水素ガスであり、大政氏が示している質量スペクトルは実際にはOHMASA-GASではなく、水の核種変換機での生成ガス(ブラウンガス)と攪拌で混入したH2Oである。
つまりグラフのOHMASA-GASとブラウンガスの比較で、OHMASA-GAS側に検出されている酸素18のクラスタガスは水の核種変換起因の酸素18ガスであり、OHMASA-GAS側の、H2Oのクラスタガスはこの水の攪拌の影響でガス中に混入した水分の影響であり、ブラウンガスは正電位で金属基板間の水を振動させているだけなので、水分を含んでいない。したがってこの質量スペクトルの上側はOHMASA-GASではなく核種変換機の電極の上下振動で生成したガスに水分が混入したガスであり、OHMASA-GASではない。
以上の大政氏の実験結果からフェムト水素分子が実在していると結論できる。したがって、フェムト重水素分子が存在し、常温核融合はフェムト重水素分子の核融合で発熱する。したがって、フェムト重水素分子が存在することで、フェムト重水素分子の核種変換実験が正しいことになり、その核種変換実験結果はターゲット原子核の原子番号が4増加すると示されているので、重陽子dの電荷が2となり重陽子は陽子2個と核内電子1個で構成されることが正しいことになる。したがって、現在の原子核モデル(原子核は陽子と中性子で構成される)はが誤りであることが証明されている。正しくは原子核は陽子と核内電子でのみで構成されて、中性子は陽子と深い電子軌道の電子との複合粒子であることが証明されている。
ここで、ブラウンガスの特異な燃焼効率の高さに関して考察すると、フェムト水素分子は余分なエネルギなしで生成されるので、通常の水の電気分解時の酸素数よりも水の核種変換で生じた酸素18の数の分だけ酸素原子数が多いことになる。ブラウンガス生成炉は特異な球形の形状で負電極の面積が正電極の面積より広いので、水素ガスが酸素16ガスよりも過剰に生成して可能性があるので、酸素16,酸素18すべてを燃焼できる可能性があり、この点でフリーエネルギー的であると推測できる。水で動く自動車内では、自動車が炉を振動させてフェムト水素分子が金属から外部に放出されるのでさらに酸素18ガスが生成される。
また、ブラウンガス炉上でブラウンガスを燃焼させると、炉内の水の温度が上昇する。通常、水の電気分解は、水の電気伝導率の高い80度以上の高温下で行うが、この観点からも、エネルギー効率が高い事が推定できる。
下記の水で動く自動車が、ブラウンガス燃焼かどうか確認してください。
ブラウンガス燃焼が産業化されたら、酸素16と、酸素18の、比率がかわり、最終的には、
酸素が地球から、減少します。大至急、調査お願いします。
こちらのご説明、非常に興味深く、私も興味を持って読ませていただきました。正直、私は専門家ではありませんが、こういったテーマにとても関心があります。ですので、恥ずかしながらも、興味本位で色々と調べてみようと思います。こうした話題について一緒に考えていけるのは、とても楽しいことだと思います。ご質問をいただけて、私も感謝しています。ありがとうございました。